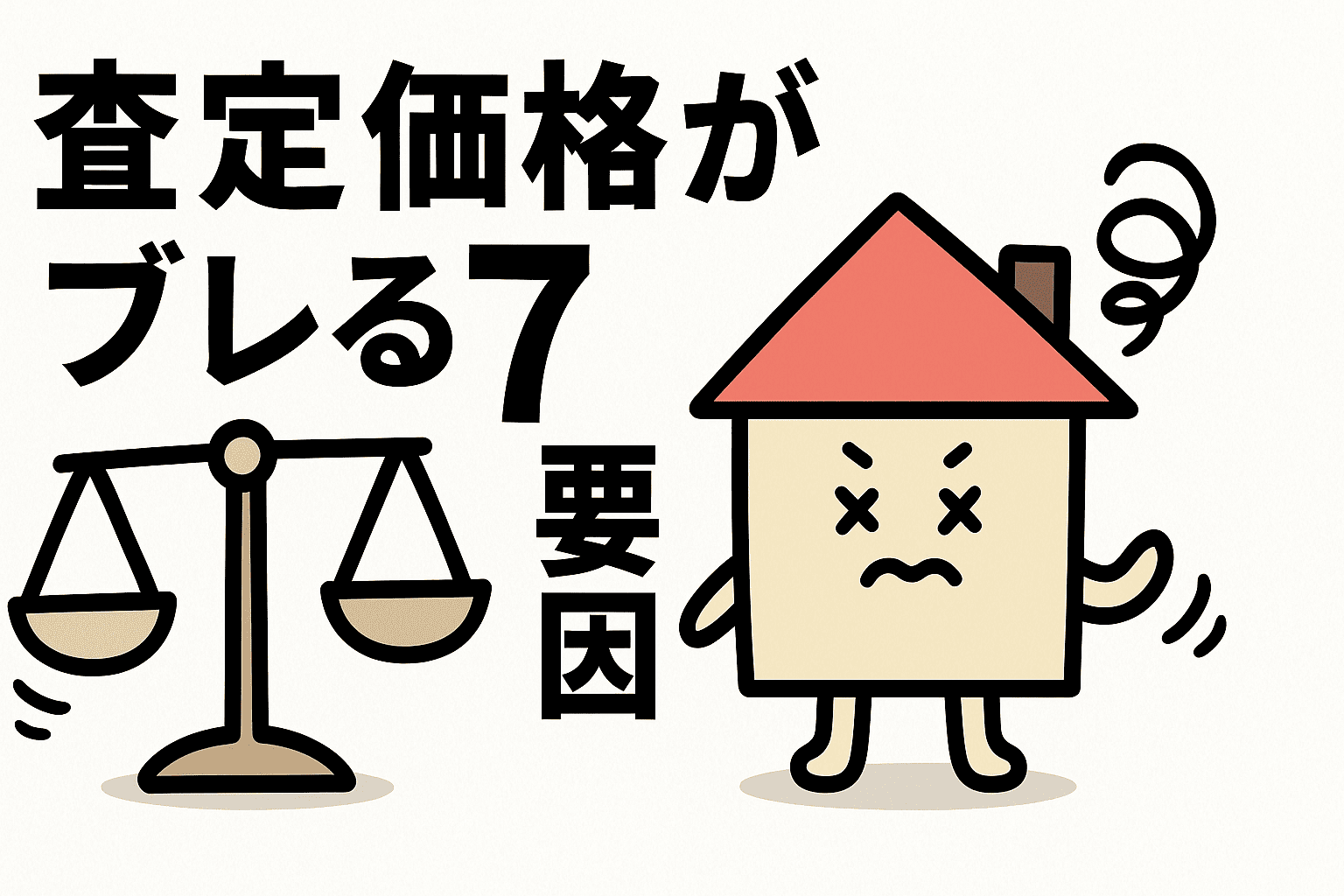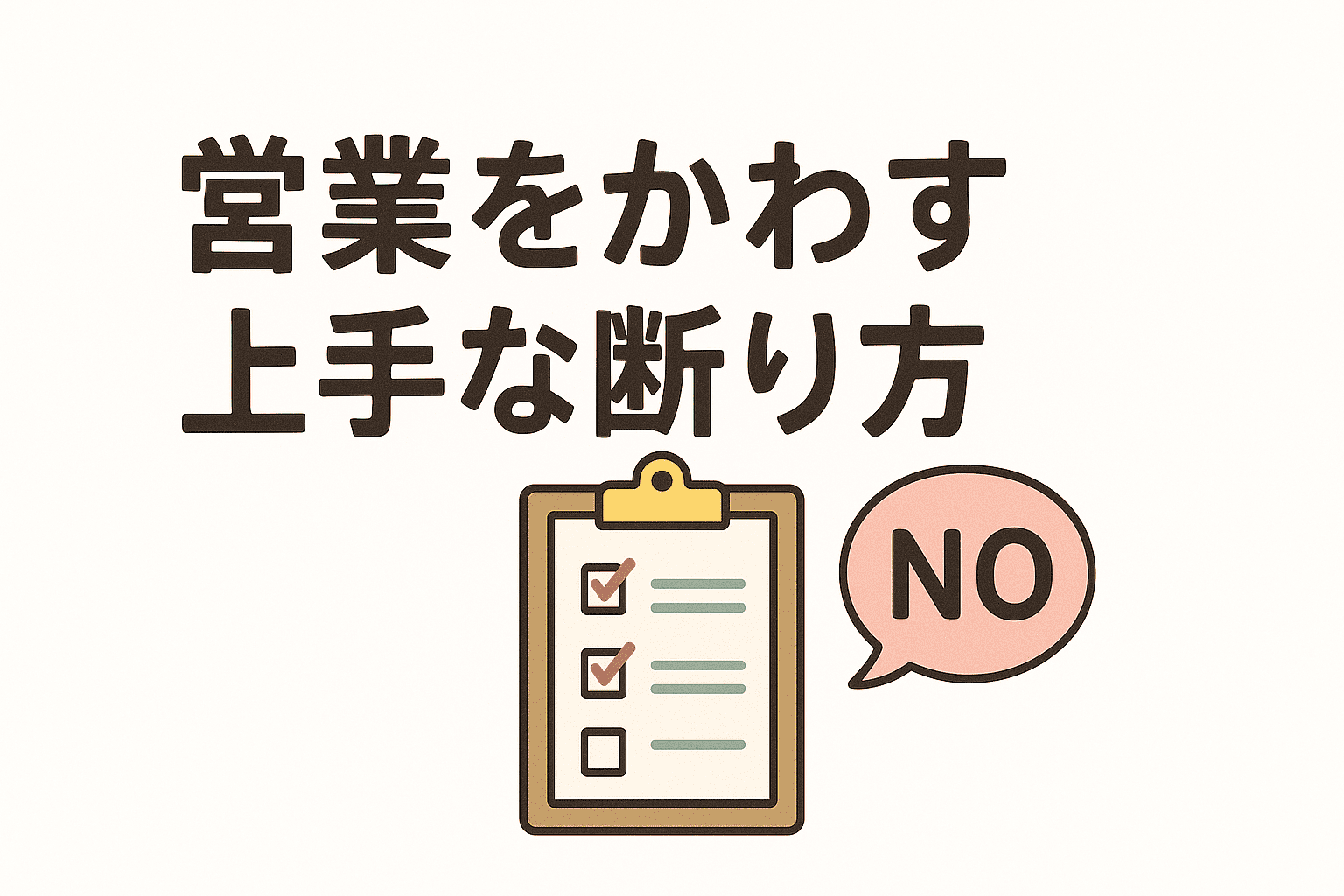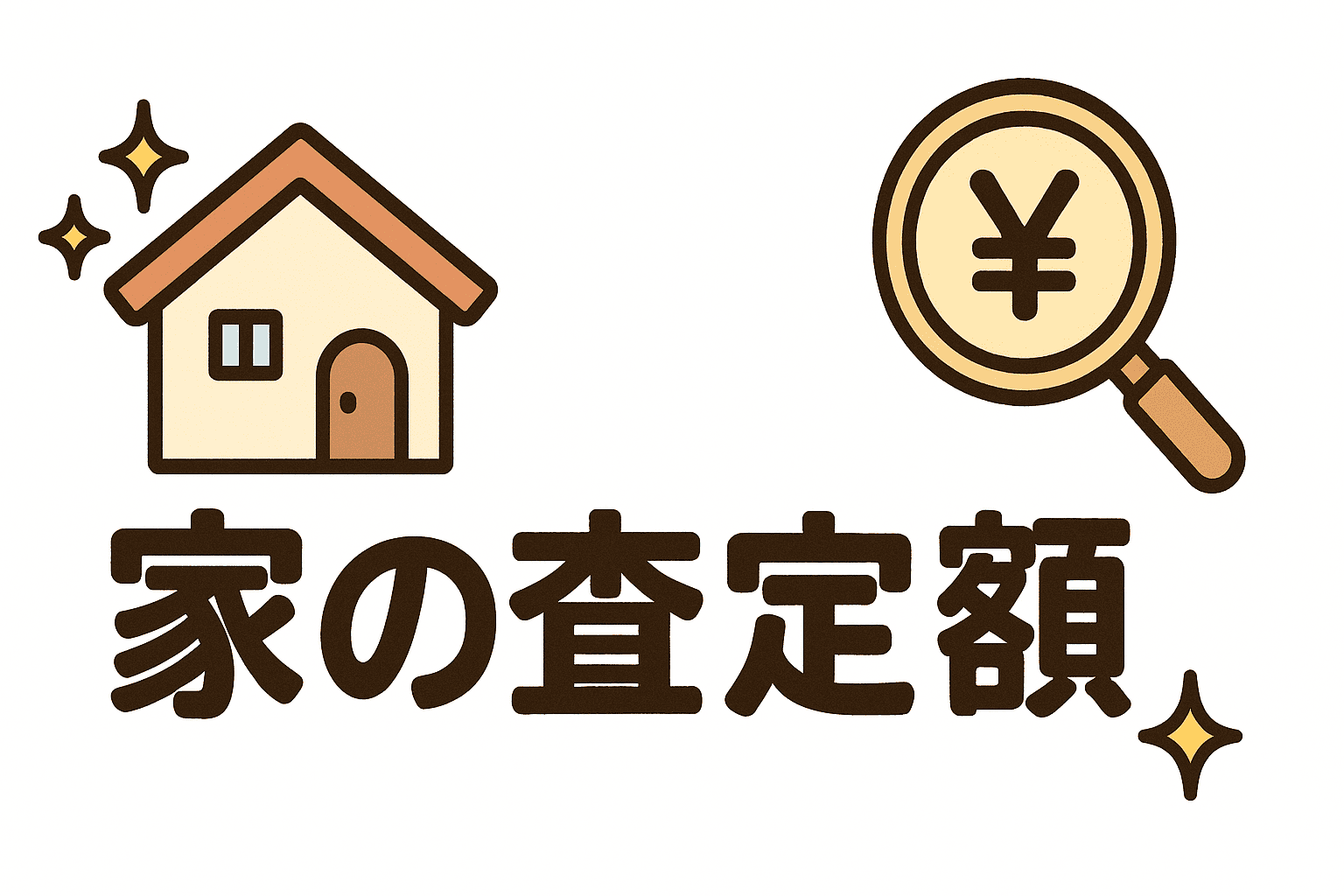1章 結論──ブレは「住戸条件×査定ロジック」で起こる。対策は中央値と事例指定
同じマンションなのに、「わが家は5,000万円、隣は5,500万円」という査定結果を受け取ると驚きますよね。
でもこれは査定がいい加減なのではなく、価格を決める「住戸そのものの特徴」と「不動産会社が用いるロジック」が掛け算になっているために起こる現象です。
階数・眺望・最近のリフォーム歴といった住戸要素が10〜15%動かし、さらに査定方式や比較事例の選び方が数%上乗せ。合計すると、70㎡マンションで最大500万円ほど差が開くことは珍しくありません。
では「いったい何が影響しているのか」を理解し、どうやってブレ幅を小さくするか――答えはシンプルです。
- 成約事例をこちらから指定する。
- 査定前提(減額・加点ルール)を開示してもらう。
- 複数社査定の中央値±3%を“実勢価格”と定義する。
この3ステップを踏むだけで、査定の誤差は±3〜4%に収まり「どの価格を信じるべきか」で迷わなくなります。
2章 査定額が大きくブレる7つのポイント——理由と対処法をセットで理解しよう
最初に「何がどれくらい価格を動かすのか」を地図のように俯瞰できるよう、下の早見表にまとめました。
そのあとで一つひとつを詳しく解説します。気になるところだけ読み進めても理解できる構成です。
| 要因 | 価格変動の目安 | 確認・対処のコツ |
|---|---|---|
| 階数・方角・眺望 | ±10〜15% | 同棟・同方角の成約事例と比較 |
| 間取り・面積 | ±5〜8% | 壁芯/登記面積のズレを把握 |
| リフォーム・設備 | ±5〜7% | 工事履歴を一覧で提示 |
| 管理状態・積立金 | −3〜5% | 増額予定を査定時に共有 |
| 比較事例の選定 | ±3〜5% | 「直近1年・同階層」を指定 |
| 査定方式(机上/訪問) | ±5%前後 | 加点・減点ルールを確認 |
| 販売戦略(高値提示) | +5〜10% | 最高値・最低値を除外し中央値で判断 |
2-1 階数・方角・眺望——お日さまの当たり方が最大の価格差を生む
最上階・南向き・前面遮蔽物なし――この3点セットは中古でも根強い人気。
70㎡マンションで坪単価が 10 万円違えば 約500 万円の差になります。
逆に北向きの低層階は洗濯物の乾きにくさや視界の閉塞感がマイナスに。
確認ポイント
- 同じマンション内で「階数」「向き」「眺望」が近い成約事例を査定根拠に入れてもらう。
- 査定担当に「窓先の建物状況をどう評価しましたか?」と必ず質問。
2-2 間取りと面積——数字が数㎡違うだけで見た目以上に総額が変わる
角部屋やワイドスパンは、家事動線が良く窓面が多いため買い手の評価が高く+5〜8%。
また広告で使われる「壁芯面積」は内壁中心を測るため、登記簿の「内法面積」より広く表示されます。
壁芯70㎡/内法67㎡なら、実質3㎡=約50万円相当の誤差が生まれる計算です。
確認ポイント
- 登記簿の面積と広告面積、両方を査定担当に示し「どちらを基準にしましたか?」と確認。
2-3 リフォーム歴と設備——“すぐ住める安心感”はそのまま価格に反映
給湯器やキッチンを更新済みのお部屋は、買い手が修理代を気にせず即入居できるため +5〜7% のプラス査定。
築浅感を残す「クロス・床全面張替え+水回り更新」セットで、概ね300〜400万円の投資に対し200〜250万円の価値上乗せが期待できます。
確認ポイント
- リフォーム履歴を時系列で一覧化し、費用総額も併記して査定担当へ提出。
- 「設備加点を何%で評価しましたか?」と聞くと査定根拠がよりクリアに。
2-4 管理状態・修繕積立金——未来のランニングコストを買い手は気にする
積立金が近く月6,000円アップ → 5年で36万円の負担増。このシナリオが見えると、買い手は価格交渉で −3〜5% を要求しやすい。
外壁やエレベーター更新が遅れている場合も同様に値引き要因になります。
確認ポイント
- 長期修繕計画書を査定依頼時に共有し「増額分をどう反映しましたか?」と質問。
2-5 比較事例の取り方——どのお部屋と比べたかで数字は変わる
同じマンションでも「直近3か月」「同階層・同方角」の成約事例を使えば精度が上がりますが、
「1年以上前」「別棟」まで含めると市況変動を受けて±3〜5%ずれるのは自然な現象です。
確認ポイント
- 依頼時に「同マンション内・直近1年・同方角」の事例を必ず含めてください、と伝える。
2-6 机上査定と訪問査定——チェック方法そのものの違いで±5%
机上査定(AI+統計)は速い反面、室内コンディションを見ないため平均値寄り。
訪問査定は劣化やリフォームを加点・減点し±5%ほど数字が動きます。
確認ポイント
- 「訪問ではどの項目で加点・減点しましたか?」と一覧で示してもらうと納得度アップ。
2-7 販売戦略——高額提示で専任契約を狙う“甘い数字”に注意
媒介契約を取りたい会社は、相場+5〜10%の高い査定を出しがちです。
契約後に「反響がないので値下げしましょう」となると、売却期間が延び最終的に相場以下で売る羽目に。
確認ポイント
- 査定額を3〜5社集め、最高値と最低値を除いた中央値を“事前の物差し”にする。
- 中央値から10%以上離れている価格は“戦略込み”と割り切り、鵜呑みにしない。
3章 “実勢価格”を±3%に収める3つのチェックリスト
せっかく複数社に査定を頼むなら、数字のブレをできるだけ小さくして「これが現実的な価格帯だね」と家族で納得したいですよね。
ここでは、私がプロの面談で必ず使う3つの質問セットをチェックリストにまとめました。プリントして机上査定メールにコピペしても、そのまま訪問査定で読み上げてもOKです。
3-1 同マンション成約事例を必ず含める
質問テンプレ
「査定書には直近1年以内、同じマンションまたは徒歩3分圏で、〈方角・階数・専有面積〉が近い成約事例を最低1件盛り込んでください。」
- 同一物件なら市況変動や設備仕様のズレが最小化
- 徒歩圏が狭いほどエリア固有の人気・供給状況を反映
成約事例が明示されると「この数字はどこから?」というモヤモヤが消え、販売戦略込みの“お世辞価格”かどうか見抜きやすくなります。
3-2 査定前提(減価・加点ルール)を開示してもらう
質問テンプレ
「訪問査定では、設備やリフォーム歴による減額・加点を一覧でご提示いただけますか?」
| 項目 | 評価 | 加減点(万円) |
|---|---|---|
| クロス全面張替え | 済 | +30 |
| 給湯器交換 | 未 | −15 |
| 積立金増額予定 | あり | −20 |
この表を出せる担当者は「数字の裏側」を説明できる人。逆に出せない場合は根拠が薄い可能性が高いため、候補から外しても後悔しません。
3-3 最高値・最低値を除いた中央値で判断
査定額が出そろったら、Excelやメモアプリに入力し並べ替え → 真ん中の数字を取ります。
例)4,800/4,950/5,000/5,050/5,300 → 〈5,000〉が中央値
- 中央値は“多数意見”のようなもの。極端な高値・安値を排除できる。
- 誤差が気になるときは中央値×0.97~1.03を“実勢レンジ”と設定。
この作業は3分で終わりますが、査定ブレの大半はここで吸収できます。
4章 ケーススタディ:築15年・70㎡で実際に300万円差が出た理由
ここからは「理屈はわかったけれど、結局どの要素がいくら動かしたの?」という疑問を、実例で確認します。
舞台は都内郊外のファミリーマンション(築15年・総戸数200戸)。同じ棟の南向き 6 階と北向き 3 階が、ほぼ同時期に査定を取りました。
| チェックポイント | 南向き6階 (A住戸) | 北向き3階 (B住戸) | 価格差の目安 |
|---|---|---|---|
| 階数・方角・眺望 | 最上階ゾーン 抜け感あり | 低層・隣接ビル | +220万円 |
| 面積・間取り | 71.8㎡/角部屋 | 69.6㎡/中住戸 | +60万円 |
| リフォーム歴 | 水回り更新済 | 原状 | +90万円 |
| 管理・積立金 | 増額なし | 来年+5,000円 | −70万円 |
| 最終査定額 | 5,120万円 | 4,820万円 | +300万円 |
ポイント解説
- 眺望+階数だけで約220万円
日当たり+夜景の抜け感が買い手層に響き、坪単価 10 万円アップ。 - 角部屋プレミアムで60万円
窓面積が増えるぶん実質面積より体感が広く、採光・通風の評価が高い。 - リフォーム済は“追加コスト不要”で90万円プラス
水回り3点セット(キッチン・浴室・洗面)を更新していたため、買い手が設備寿命を気にせず即入居できる。 - 積立金増額予定は逆にマイナス70万円
B住戸は来期から月5,000円アップが決まっており、将来負担として値引きが入った。
2つの住戸は
- 築年数、建物構造、管理組合規約:全く同じ
- 専有面積差:たった 2.2㎡
にもかかわらず、査定額は約300万円開きました。
ここで見えてくるのは、「眺望・リフォーム・将来コスト」の情報を査定担当にどう提示するかが価格を大きく左右するという事実です。
もし B 住戸がリフォーム計画と積立金増額を事前に説明し、買い手の不安を解消していたら? 査定マイナスは半減していた可能性があります。
5章 よくある質問(FAQ)
Q1 「リフォームしてから査定したほうが高くなる?」
結論:見た目のリフォームより“水回り+給湯器”がコスパ高。
壁紙・床だけを張り替えても、査定加点はせいぜい +1〜2%。一方でキッチン・浴室・給湯器の3点セットを更新すると、買い手は「あと10年は大きな出費がない」と判断し+5〜7%の加点が期待できます。
もし総額100万円以内で水回りを更新できるなら、査定アップ額がリフォーム費を上回る“黒字リフォーム”になるケースが多いです。
Q2 「賃貸に出してから売ると価格は下がる?」
賃借人が居住中=“オーナーチェンジ物件”は、実需向けより5〜10%安くなるのが一般的です。理由は、買い手がすぐに住めず、退去交渉や原状回復費用を織り込むから。
ただし
- 駅徒歩3分以内
- 築20年以上の都心ヴィンテージ
など賃料利回りが高い物件は投資家需要で価格が維持されやすいので、「家賃 ×12÷利回り」を目安に売値を設定するとブレが少なくなります。
Q3 「低層階はやっぱり売りにくいの?」
1〜2階でも、専用庭付き・テラス付きならファミリー層に人気があり、同フロア内で+3%ほど上乗せされることがあります。
逆に道路に面して騒音がある場合は売却期間が伸びやすいので、査定依頼時に「販売想定期間」も聞いておくと後のスケジュール調整がラクになります。
Q4 「査定額と実際の売却価格はどれくらいズレる?」
複数社査定の中央値を基準に14日以内で価格調整すれば、最終成約価格は中央値の±3%に収まるケースが約8割。鉄則は
- 査定中央値で売り出す
- 2週間反響ゼロなら▲3%値下げ
この“14日ルール”を媒介契約時に合意しておくと、ダラダラ値下げを避けて短期で売り切れやすくなります。
Q5 「子どもが小さいので内覧準備が大変。査定に影響しますか?」
玩具やベビーカーがある程度置いてあっても査定は変わりません。ただし生活感の強いキッチンと水回りは、写真映えが落ちると内覧予約数が減ります。
玄関と水回りだけでも“1カゴ収納”で物を一時退避できるようにしておくと、査定担当も買い手も「丁寧に住んでいる印象」を抱きやすく、減点を防ぐ効果があります。
6章 おわりに──“価格のモヤモヤ”を今日スッキリさせよう
ここまで読んでくださったあなたは、査定額がブレる仕組みと、そのブレを小さくする方法をすべて手に入れました。
やることは意外とシンプルです。
- AIまたは机上査定で3〜5社から数字を取る(メール連絡のみでOK)。
- 早見表を見ながら、成約事例の条件と加点・減点ルールを質問する。
- 最高値・最低値を外し、中央値±3%を“わが家の今の値段”としてメモ。
わずか1時間で完成するこのメモがあれば、
「いつ売る?」「リフォームは元が取れる?」といった悩みが、数字で判断できるようになります。
お子さんの寝かしつけが終わったあと、スマホ片手にまずはAI査定を1件だけ試してみませんか?
数字が届いた瞬間、モヤモヤは小さく、次の一歩はずっとクリアになります。
 いえマネLIFE
いえマネLIFE