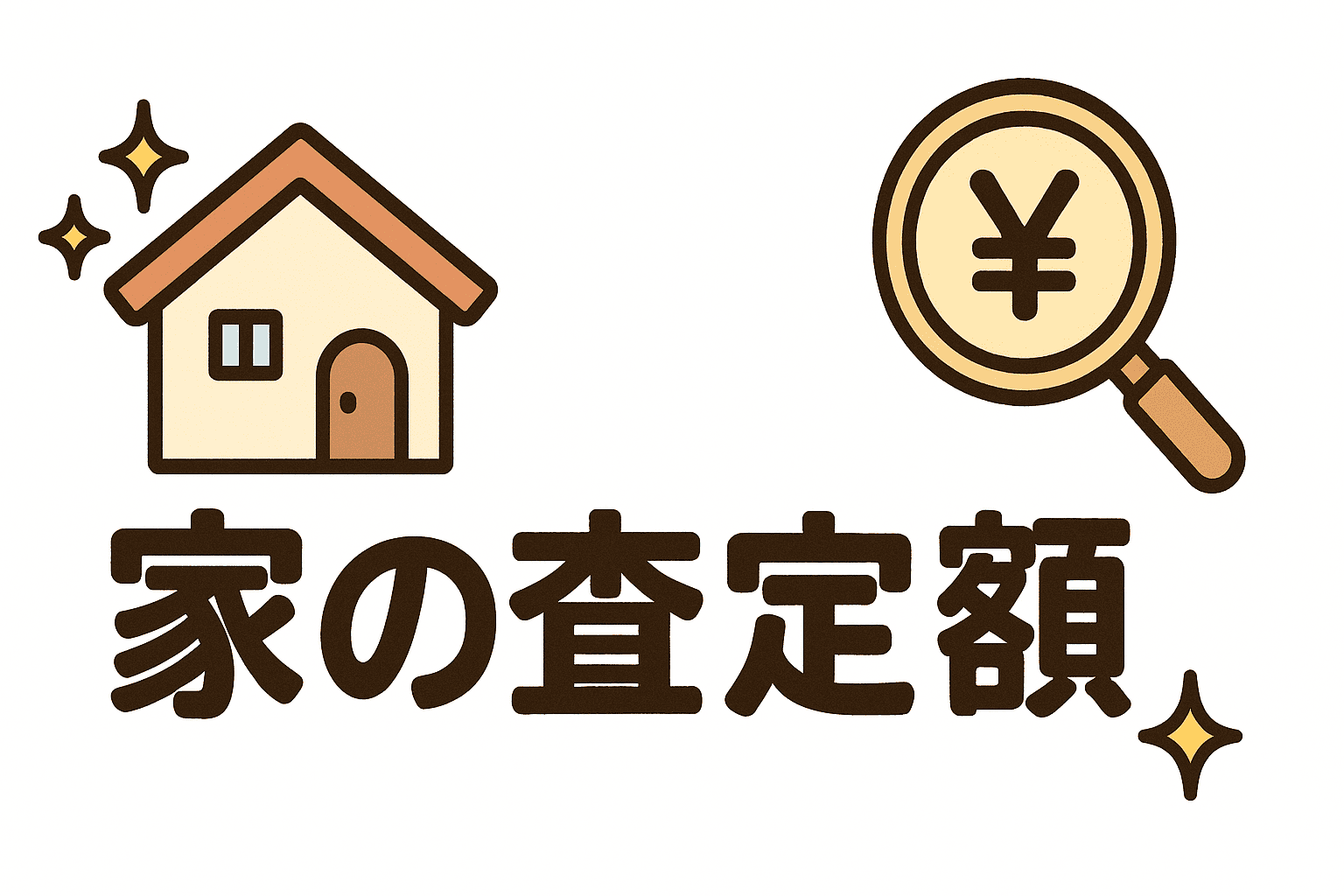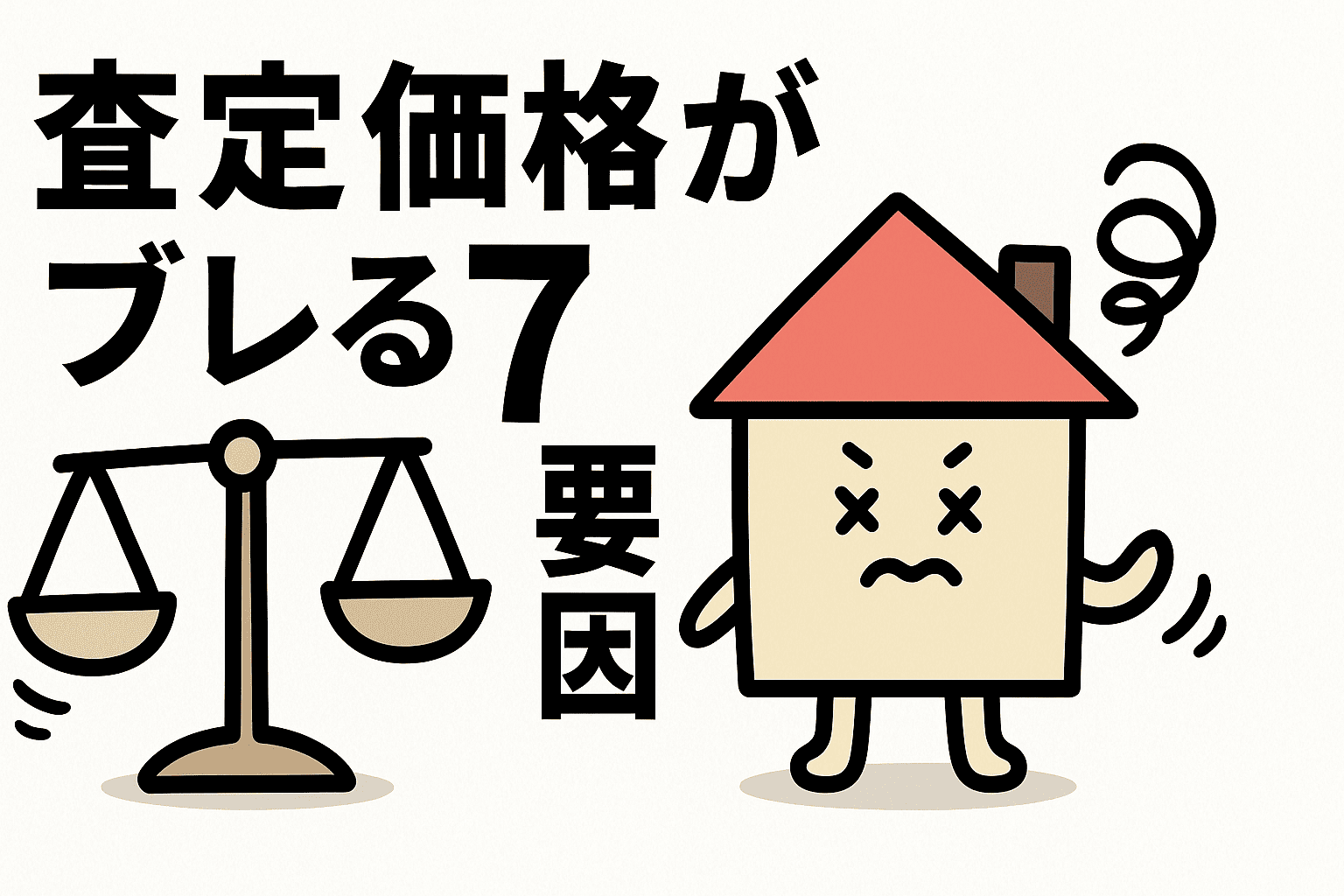1章 結論──査定は「基準単価+7つの調整」で決まる
「査定ってプロの勘で決まるのかな?」と感じたことはありませんか?
実際には、とても論理的な“足し算”で組み立てられています。まず、査定担当者は〈直近の成約事例〉から“基準単価”(1㎡あたりの平均価格)を引っぱってきます。
その後、次の7項目でプラスやマイナスを付け足し、最後に足し合わせた数字が、あなたのお部屋の査定額になるのです。
- 立地(駅徒歩・学区・買物施設)
- 階数・方角・眺望
- 専有面積と間取り
- 室内コンディション(リフォーム・設備更新)
- 管理状態と修繕積立金
- 直近成約事例の精度
- 市況と販売戦略(在庫数・金利)
ポイントは「基準単価 × 専有面積」=素点に、7項目を%で加減点するだけというシンプルさ。
仕組みを知れば、「なぜ隣の部屋と〇百万円違うの?」のモヤモヤが数字で説明できるようになります。
2章 スタート地点:基準単価はこうして引っぱってくる
査定の“土台”になる数字は、不動産会社がレインズ(業者間の成約データベース)から抜き出す「最近いくらで売れたか」というリアルな取引価格です。
ここを押さえれば、以降の加点・減点がどんなに動いても“出発点がズレていた”という事態を防げます。
2-1 最新レインズ成約をどう絞るか
プロは、まず下の3条件で検索をかけます。
1. エリア:同じマンション内 → 見つからなければ徒歩5分圏で拡張
2. 築年:±3年以内
3. 成約時期:直近1年以内(相場の上げ下げを反映しやすい)
例)同じ棟に直近成約が1件しかない
→ 隣接ブロックの類似マンションを「距離補正−2%」で採用
こうして集めた3〜5件の坪単価(万円/㎡)を平均したものが基準単価になります。
平均ではなく中央値(真ん中の値)を使う会社もありますが、いずれも「極端な高値・安値を排除して歪みを取る」考え方は同じです。
2-2 半径・築年・階数で“補正係数”を掛ける
成約事例と査定対象がピタリ同じ条件とは限りません。
そのため、以下3つのギャップには補正係数という“微調整の定規”を当てます。
| ギャップ | 典型的な補正幅* | チェックのしかた |
|---|---|---|
| 距離(駅徒歩) | −0.5% / 30秒差 | 依頼時に「徒歩○分」と正確に伝える |
| 築年 | −1% / 年 | 長期修繕計画で築年を補足 |
| 階数差 | +1〜1.5% / 1フロア上 | 「階別単価表ありますか?」と質問 |
*首都圏・ファミリーマンションの目安。会社により微調整。
- 距離補正 … 徒歩7分の事例を徒歩5分の部屋に当てはめる場合、+1%上乗せ。
- 築年補正 … 築13年の事例を築10年の部屋に当てはめる場合、+3%上乗せ。
- 階数補正 … 3階成約を6階へ当てはめる場合、+3〜4.5%上乗せ。
このように、基準単価は“似ている事例を複数拾い、ズレを小さな係数で調整”することで精度を高めています。
査定面談では、「今回の基準単価はどの事例を使いましたか? 補正は何%入っていますか?」と2つ続けて聞くだけで、土台が堅い数字かどうかが見抜けます。
基準単価をしっかり把握できたら、あとは次章でご紹介する7項目の加点・減点を足し引きするだけで“わが家専用の査定額”が完成します。
3章 加点・減点を生む7つのチェックポイント──数字の動き方を“物語”でイメージしよう
査定担当者は、基準単価のあとに7つの物差しを当てながら “あなたのお部屋だけの値段” に調整していきます。
どれも日常の感覚に落とし込めば難しくありません。ここでは「イメージしやすさ」を重視し、ストーリー仕立てでポイントごとに掘り下げていきます。
3-1 駅距離と生活利便──家族が毎日歩く5分をどう見る?(±15%)
朝の通勤、ベビーカーでの買物、塾帰りの夜道…。駅までの“体感距離”は暮らしのテンポを決めます。
- 徒歩3〜5分圏:「子どもと手をつないでも苦にならない」と感じる人が多く、+8〜12%のプレミアム。
- 徒歩10分超:雨の日・暑い日の負担を想像し、−5%前後の補正がかかります。
さらにスーパー、保育園、公園が3分圏にそろえば+2〜3%の上乗せ。査定時に「駅5分・スーパー2分・保育園3分」と“数字で言語化”して伝えると、担当者が加点を逃しません。
3-2 階数・方角・眺望──窓からの景色にいくら払う?(±10%)
買い手は内見でドアを開けた瞬間に「わぁ明るい!」と感じるか、「思ったより暗い…」と感じるかで温度差がつきます。
- 最上階 × 南西向き × 抜け感あり → +10%前後。
- 低層 × 北向き × 隣接ビル → 0〜−5%。
でも低層北向きでも「前面が低層住宅で空が広い」なら ±0 付近に戻せることも。窓先の写真や昼と夕方の採光動画をスマホで見せると、査定担当のイメージを補完できます。
3-3 専有面積と間取り──「数字」と「体感広さ」は別モノ(±8%)
たとえば 71.8㎡の角部屋と 68.0㎡の中住戸。数字は 3.8㎡差ですが、角部屋は窓面が多く体感が広いため+5〜8%の加点が一般的です。
また、壁芯面積(広告)と登記面積(登記簿)に 2〜3㎡差がある物件なら、査定担当に「どちらを基準にしましたか?」と質問しましょう。大半は広い方(壁芯)で計算しますが、聞くだけで面積補正の有無が明確になります。
3-4 室内コンディション──“水回り3点”は査定アップの即効薬(±7%)
テレビでよく見る「壁紙だけ張り替えて高く売る」は実はコスパが低め。査定が一番反応するのはキッチン・浴室・給湯器を10年以内に交換しているかどうかです。
- 3点セット更新済み → +3〜5%(約150〜250万円)
- 未更新 → −3%ほど値引き想定で査定
クロスやフローリングは内覧映え目的なので、査定加点は+1〜2%。先に水回りを整え、予算に余裕があれば壁紙で仕上げるのが王道です。
3-5 管理状態と修繕積立金──未来のお財布を買い手は計算する(−5%〜±0)
管理が行き届き、積立金が堅実に積まれている物件は“安心料”として評価が落ちにくい一方、来年から月5,000円アップが決まっていると−3〜5%の調整が入り得ます。
コツは「先手で情報開示」。長期修繕計画書や総会資料をPDFで渡し、増額幅と時期を伝えれば、査定担当も“知らなかった減点”をせずに済むからです。
3-6 直近成約事例の精度──「どこを比べたか」で±5%動く
成約事例が
- 同マンション
- 同方角・階数
- 1年以内
に近ければ近いほど基準単価の信頼性が高まります。査定書に条件が書かれていない場合は、「事例の距離・階数・時期を教えてください」と一言添えるだけで担当者が詳細を明示してくれます。
3-7 市況と販売戦略──“いま”の在庫と金利が最後の微調整(±3〜5%)
- 在庫増+金利上昇 → 売れ残りリスク回避で−3〜4%低めスタート
- 在庫少+低金利継続 → “高値チャレンジ”提案で+3%程度上乗せ提案
もし提案価格が他社より10%以上高ければ、「販売戦略として高め設定ですか?」と確認を。
売出2週間で反響ゼロの場合は▲3%値下げを事前に合意しておくとダラダラ下げを防げます。
4章 実際の算出フロー──“数字の川下り”で査定額が決まるまで
ここからは少しマニアックに、基準単価が最終的な「査定価格」へ流れ着くまでの計算ステップを順番に追ってみましょう。
流れを川の上流から下流へたどるイメージで読むと、数字の動きがグッとつかみやすくなります。
4-1 上流:基準単価 × 専有面積で“素点”をつくる
例として、直近1年の同マンション成約3件の平均単価が 73万円/㎡だったとします。
専有面積が 70.0㎡ なら、まずは
73万円 × 70.0㎡ = 5,110万円
ここまでが“基準のまっさらな価格”です。
この数字に7項目の加点・減点を足し引きしていくのが次のステップ。
4-2 中流:7項目を%で加減点する
| 項目 | 評価 | 加減率 | 調整額 |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩5分 | 良 | +8% | +409万円 |
| 南向き6階 | 良 | +6% | +307万円 |
| 角部屋71㎡※ | 良 | +3% | +154万円 |
| 水回り更新済 | 良 | +4% | +205万円 |
| 積立金増額なし | 可 | ±0% | ±0万円 |
| 成約事例精度 | 高 | +1% | +51万円 |
| 在庫少・低金利 | 追い風 | +2% | +102万円 |
※登記面積は 70.5㎡/壁芯71.0㎡。査定は壁芯を採用
加減率は会社によって0.5〜1ポイント程度ブレますが、考え方は共通です。
「今うちがどの欄にいくらで書かれるか」をイメージすると、何を整えれば良いかが見えてきます。
4-3 下流:調整額を合計し“査定価格”が確定
基準価格 5,110万円 + 加点合計 +1,228万円 = 最終査定 6,338万円
ここまで来て初めて、担当者は「6,300万〜6,400万円で売れそうです」と口にします。
もし別の会社が6,700万円を提示したら——
- 基準単価を引っぱるエリアが違う?
- 加点率が相場より大きい?
と“川の途中”を点検すれば、数字が高い理由/危うい理由を具体的に突き止められるわけです。
このフローを知っておくと、査定書のどこを見れば良いか迷いません。
5章 サンプル計算──「高評価住戸」と「減点住戸」を並べてみる
ここでは築15年・70㎡マンションの2つのお部屋を例に、
先ほどのフローに実際の数字を当てはめてみましょう。
| 条件 | A住戸(高評価ケース) | B住戸(減点ケース) |
|---|---|---|
| 階数・方角・眺望 | 南西向き 6階/抜け感あり | 北向き 2階/前面ビル |
| 室内コンディション | 水回りフル更新・壁紙張替え | 原状/給湯器13年目 |
| 積立金 | 増額予定なし | 来年+5,000円/月 |
| 直近市況 | 在庫少・低金利 | 同上 |
5-1 A住戸:加点フル盛りの計算例
基準単価 73万円 × 70㎡ = 5,110万円
+ 階数・眺望 +6% = +307万円
+ 水回り更新 +4% = +205万円
+ 駅徒歩5分 +8% = +409万円
+ 在庫少 +2% = +102万円
合計 = 6,133万円
ポイント
- 眺望と水回りだけで+512万円上乗せ。
- 積立金が健全なので減点ゼロ。数字の伸びが素直に効いています。
5-2 B住戸:減点が重なった計算例
基準単価 73万円 × 70㎡ = 5,110万円
− 眺望・方角 −5% = −256万円
− 給湯器13年 −2% = −102万円
− 積立金増額 −3% = −153万円
+ 駅徒歩5分 +8% = +409万円
+ 在庫少 +2% = +102万円
合計 = 5,110万円
ポイント
- プラス要素は駅近・市況のみで+511万円。
- しかし眺望・設備・積立金の−511万円が打ち消し、
最終的には“基準価格どおり”に着地しました。
5-3 内訳を比べると何が見える?
| 項目 | A:調整額 | B:調整額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 階数・眺望 | +307万 | −256万 | 563万 |
| 室内更新 | +205万 | −102万 | 307万 |
| 積立金 | 0万 | −153万 | 153万 |
| 市況・駅距離 | +511万 | +511万 | — |
| 合計 | +1,023万 | 0万 | 1,023万 |
AとBの査定差は約1,020万円。その7割以上を作っているのが
「眺望」と「水回り3点+給湯器」と「積立金の将来負担」という3項目です。
逆に言えば、B住戸が
- 給湯器を更新(−2%→±0%)
- 積立金増額時期を購入後5年以上先に延期(−3%→−1%)
だけでも、査定は+150〜200万円伸びる余地があります。
数字を“分解”して眺めると、どこを改善すると上がる/下がるが手に取るようにわかります。
次章では、こうした気づきに答える形で、査定にまつわる「よくある質問」を一気に解消していきましょう。
6章 よくある質問(FAQ)
Q1 査定書に“成約事例3件”が載っていません。お願いしても良い?
もちろんです。成約事例は査定ロジックの原材料。
「同マンション内・直近1年・同方角」で1件以上入れてもらうよう依頼しましょう。
もし「公開できない」と渋る会社があれば、基準単価の信頼性が担保できないため、他社に切り替えるのが無難です。
Q2 水回りを直す予算が限られています。どこから手を付けるべき?
査定加点が大きい順は①給湯器 → ②浴室 → ③キッチンです。
- 給湯器:10〜15年目で寿命。交換済みだと+2〜3%の加点。
- 浴室:ユニットバス交換で+1〜2%加点+内覧印象UP。
- キッチン:デザイン性より「食洗機やIH追加」の機能強化が評価されやすい。
50万〜80万円の部分リフォームでも、査定アップ額で元が取れる可能性があります。
Q3 積立金が来年上がる予定です。査定にどう影響しますか?
増額幅×残存期間を「現在価値」に引き直して−3〜5%の減点が一般的です。
例:月5,000円増額・5年先→累計30万円
査定担当が把握していないと、後で買い手から値下げ要求が来る二重マイナスに。
総会資料をPDFで共有し、あらかじめ減点幅を確定させるほうが安全です。
Q4 高い査定を出してくれた会社だけ信じても大丈夫?
「基準単価×専有面積=素点」が他社と同じなら、差額は加点率か販売戦略のどちらかが大きいと考えられます。
- 加点根拠→前章の7項目に沿って説明できるなら OK。
- 販売戦略→“高値チャレンジ”提案。14日反響ゼロ時の値下げルールを書面で合意できれば、試してみる価値があります。
Q5 低層北向きでも、査定を上げる現実的な方法は?
眺望と採光は変えられませんが、「即入居可」+「管理の透明性」で減点を埋めることが可能です。
- 水回り3点のメンテ履歴を時系列で提示
- 長期修繕計画と積立金残高を開示し、将来負担の不安を解消
- 家具配置例を用意し、北向きでも明るく暮らせるレイアウトを提案
これらをそろえると、階数・方角のマイナスが−10% → −4〜5%まで緩和した事例があります。
7章 おわりに──“わが家の値段”は今日30分で調べられる
査定ロジックの核心は「基準単価×7項目の調整」。
つまり基準単価さえ押さえれば、残りは暮らしの中で整えられるということです。
Step 1 基準単価を5分でチェック
- SUUMOやHowMaなどのAI査定に住所と専有面積を入力。
- 届いた価格を面積で割り、㎡単価をメモ(例:73万円/㎡)。
Step 2 同マンションの最新成約を2件探す(約15分)
- レインズMarket Informationや住民の口コミ掲示板で、同じ棟・同階層・1年以内の成約単価を確認。
- AI査定の㎡単価と±5%以内なら「基準単価OK」と判断。
Step 3 7項目セルフチェックで“加点できる所”を洗い出す(10分)
- 水回りの更新年、積立金の増額予定、窓先の写真、伸ばせそう&減点を防げそうなポイントに丸を付ける。
- 丸を付けた項目を査定依頼メールに追記すると、加点漏れがほぼゼロに。
ここまで30分。数字と根拠がそろったメモは、そのまま家族会議の資料になります。
「売る・貸す・このまま住む」――どの選択肢でも、“よく分からない”が“数字で考えられる”に変わるはずです。
今夜、スマホでStep 1だけでも試してみませんか?
価格の“出発点”が見えた瞬間、次の一手はもう見えています。
 いえマネLIFE
いえマネLIFE